
法人保険における経費とは?損金算入のルールや経理処理をわかりやすく解説
「法人保険における経費処理の方法とは?」
「損金ルールはどのように変更された?」
と疑問をお持ちの方がいるかもしれません。
法人保険の経費処理の方法は、個人保険と異なります。
2019年の税制改正により、損金ルールも変更されたため、最新情報を理解した上で適切に処理する必要があります。
今回の記事では、法人保険における経費の基礎知識をはじめ、経費・損金のルール、法人保険の経費に関するよくある質問について詳しく解説します。
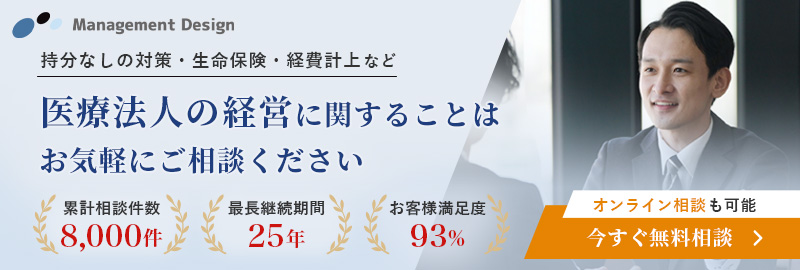
法人保険における経費について



まずは法人保険の経費に関する基礎知識をおさらいしておきましょう。
法人保険とは
法人保険とは、法人が契約者となる保険のことです。
個人が契約者となる保険は「個人保険」として区別されます。
法人保険にはさまざまな種類がありますが、大きく分けると以下の3種類です。
| 法人保険の種類 | 概要 |
|---|---|
| 生命保険 | 経営者や従業員の死亡に備える保険 |
| 損害保険 | 事業活動における事故などのリスクに備える保険 |
| 第三分野の保険 | 経営者や従業員の病気やケガに備える保険 |
法人保険は退職金の積み立てとして活用されることもあります。
法人保険で退職金を準備する方法については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:法人保険で経営者・役員の退職金を準備する方法を解説
法人保険の損金とは
損金(そんきん)とは、法人税の計算時に収益から差し引ける費用・損失のことです。
法人保険においては、企業が月々支払う保険料を損金に算入することが可能です。
そのため、法人税の負担を軽減するために法人保険が活用されることがありました。
しかし、現在は2019年の税制改正により、経費・損金のルールが厳格化しています。
経費・損金のルールについて、以下で詳しく確認していきましょう。
法人保険における経費・損金のルールとは
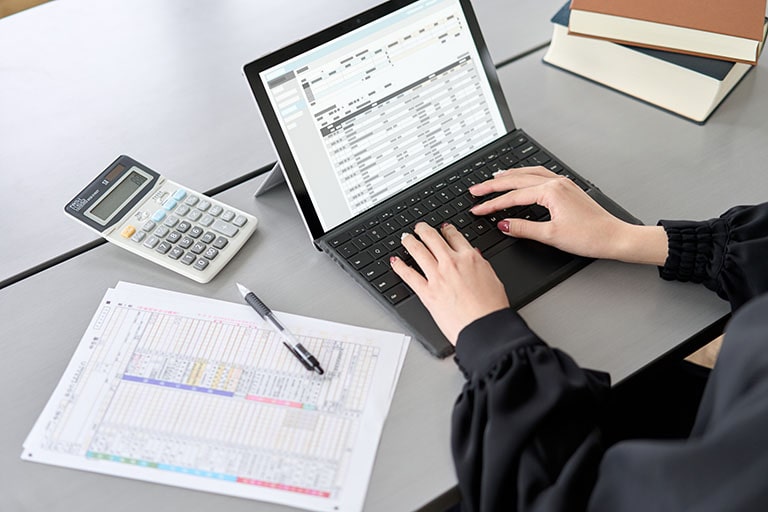
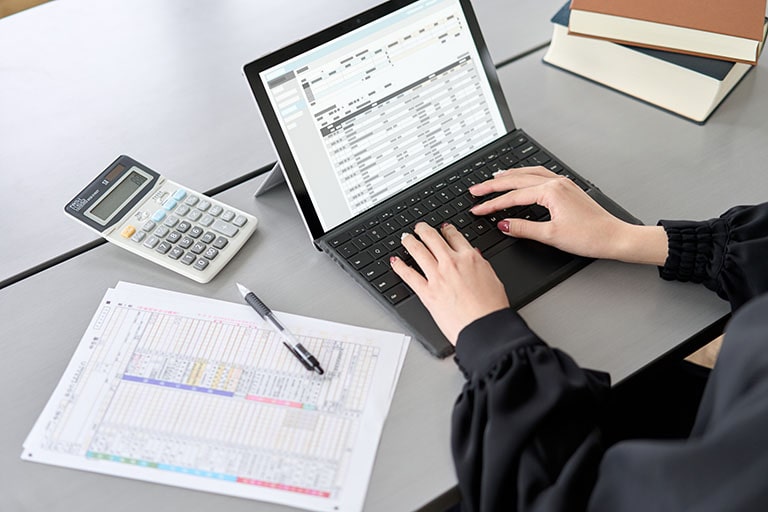
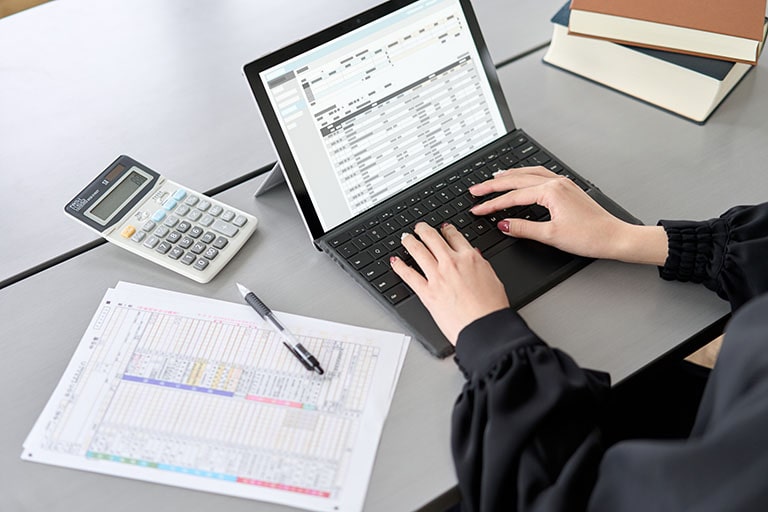
法人保険に加入する上で、経費・損金のルールについて理解しておくことは重要です。
以下で、税制改正による新しいルールを確認していきましょう。
2019年の税制改正により損金が見直しされた
国税庁により法人保険における経費・損金のルールが見直され、2019年10月から新税制が適用されました。
今まで全額を損金算入できていた保険であっても、一部しか損金算入できないように変更されているため注意してください。
税制改正が実施された背景には、本来の法人保険の目的ではなく、税金対策に重きを置く企業が増加したことが関係しています。
税制改正の内容について、詳しく見ていきましょう。
税制改正の内容
2019年の税制改正により、損金算入のルールが変更されました。
新ルールで損金算入できる割合は以下の通りです。
| 最高解約返戻率 | 資産計上必要期間 | 損金算入割合 | 取崩期間 |
|---|---|---|---|
| 50%以下 | 全額損金算入 | ||
| 50%超70%以下 | 保険期間開始日~保有期間4割の期間まで | 60% | 10年目まで:100%-(最高解約返戻率×90%) 11年目以降:100%-(最高解約返戻率×70%) |
| 70%超85%以下 | 40% | ||
| 85%超 | 保険期間開始日~最高解約返戻率となる期間まで | 【10年目まで】100%-(最高解約返戻率×90%) 【11年目以降】100%-(最高解約返戻率×70%) |
解約返戻金額が最も高い金額となる期間経過後から終了まで |
参考:第3節 保険料等|国税庁
上記のように最高解約返戻率が高い商品ほど、損金に計上できる割合が低くなります。
【種類別】法人保険の経費・経理処理をわかりやすく解説
法人保険の経費・経理処理は、種類によって変わってきます。
以下で種類別に経費・経理処理の方法について確認していきましょう。
定期保険
定期保険とは、契約時に取り決めた一定期間を保障する保険です。
契約期間中に死亡や高度障害状態になった場合に保険金が支払われます。
保険料支払期間における保険料の経理処理は、以下の通りです。
| 最高解約返戻率 | 経理処理 | ||
|---|---|---|---|
| 50%以下 | 全額損金算入 | ||
| 50%超70%以下 | 【保険期間の前半40%の期間】 損金算入:60%資産計上:40% |
【保険期間の40~75%の期間】 当期保険料を全額損金算入 |
【保険期間の残り25%の期間】 当期保険料を全額損金算入 資産計上した前払保険料を期間按分して損金算入 |
| 70%超85%以下 | 【保険期間の前半40%の期間】 損金算入:40%資産計上:60% |
||
| 85%超 | 〈資産計上期間〉 | ||
| ①:保険期間の開始日〜最高解約返戻率となる期間終了日 | ②:①の期間経過後、年換算保険料における解約返戻金の増加額の割合が70%を超える場合、超えるまでの期間終了日 | ③:①②の資産計上期間が5年未満の場合、5年(保険期間が10年未満の場合、保険期間の50%を経過する日まで) | |
| 【保険期間開始から10年経過する日までの期間】 損金算入:保険料×最高解約返戻率×10%資産計上:残り90% |
【保険期間の11年目以降】 損金算入:保険料×最高解約返戻率×30%資産計上:残り70% |
解約返戻金が最も高い金額となる期間から保険期間終了日までに、これまで資産計上した前払保険料を期間按分して損金算入 | |
第三分野保険
第三分野保険とは、経営者や従業員の病気やケガに備える保険のことです。
例えば、医療保険やがん保険、介護保険など、さまざまな種類があります。
第三分野保険は保険のタイプによって、経理処理の方法が変わってきます。
| 保険のタイプ | 経理処理 |
|---|---|
| 一定期間の保障 | 定期保険と同じ |
| 終身タイプの保障(全期払い) | |
| 終身タイプの保障(短期払い) | 【1人あたりの年間支払い保険料合計が30万円以下】 全額損金算入 【1人あたりの年間支払い保険料合計が30万円超】 ・年間保険料×払込期間÷保険期間の金額を1年分の保険料として損金に算入し、残りを資産計上する。 ・払込期間終了後は、資産計上したものを毎年上記計算式の金額分取り崩して損金に算入 |
養老保険
養老保険とは、死亡保障と貯蓄の両方を兼ね備えた保険のことです。
万が一死亡した場合は「死亡保険金(もしくは高度障害保険金)」、契約終了時に存命の場合は「満期保険金」が支払われます。
| 死亡保険金受取人 | 満期保険金受取人 | 経理処理(保険料支払期間中) | 経理処理(保険金受取時) |
|---|---|---|---|
| 法人 | 法人 | 全額資産計上 | 資産計上した支払保険料と、受取保険金の差額を雑収入として益金に計上 |
| 役員・従業員 | 役員・従業員 | 全額損金算入(支払保険料は給与扱いとなり、税金が発生) | 資産計上した支払保険料は、雑損失として損金に算入 |
| 法人 | 損金算入:50%(福利厚生費として)資産計上:残り | 【死亡保険金】資産計上した支払保険料を、雑損失として損金に算入 | |
| 【満期保険金】資産計上した支払保険料と、満期保険金の差額を雑収入として益金に計上 |
終身保険
終身保険とは、死亡保障が一生涯続く保険のことです。
保険料が死亡保険金・解約返戻金よりも大きいかどうかで、経理処理の方法が変わってきます。
| 保険料支払期間中 | 保険金受取時 | |
|---|---|---|
| 全額資産計上 | 【保険料が死亡保険金・解約返戻金よりも大きい場合】 差額分を雑収入として益金計上 |
【保険料が死亡保険金・解約返戻金よりも小さい場合】 差額分を雑損失として損金に算入 |
法人保険の経費に関するよくある質問



ここでは、法人保険の経費に関するよくある質問を紹介します。
法人保険で全額損金算入できる30万円特例とは?
2019年の税制改正により、保険料の損金ルールが厳格化されました(これまで全額損金と呼ばれていたような法人保険がなくなりました。)
しかし、特定の条件を満たせば全額損金できる例外ルールが存在します。
それが「30万円特例」と呼ばれるルールです。
年間支払保険料(被保険者1人あたり)の合計が「30万円以下」になる場合、保険料全額を損金として計上できます。
対象となる保険は「最高解約返戻率が70%以下の定期法人保険」もしくは「終身タイプの第三分野保険(短期払い込み)」の2種類です。
社長が生命保険に法人契約した場合、経費に算入できる?
社長が生命保険に法人契約した場合、保険タイプによっては経費に算入できます。
しかし、保険料を受け取る際に法人税が課税されるため、税金対策としての効果はあまりないでしょう。
養老保険や終身保険など貯蓄性のある保険タイプは、資産として計上されます。
法人保険で4割損金扱いになるケースは?
法人保険で4割が損金となるケースとして、最高解約返戻率が「70%超〜85%以下」の場合が挙げられます。
定期保険の場合は「最高解約返戻率が70%超〜85%以下」かつ「保険期間の前半40%の期間」である場合、4割が損金となります。
法人保険で全額損金扱いになるケースは?
法人保険で全額損金扱いになるケースとして、「最高解約返戻率が50%以下」が挙げられるでしょう。
加えて、「年間支払保険料(被保険者1人あたり)の合計が30万円以下」の場合も全額損金扱いとなります。
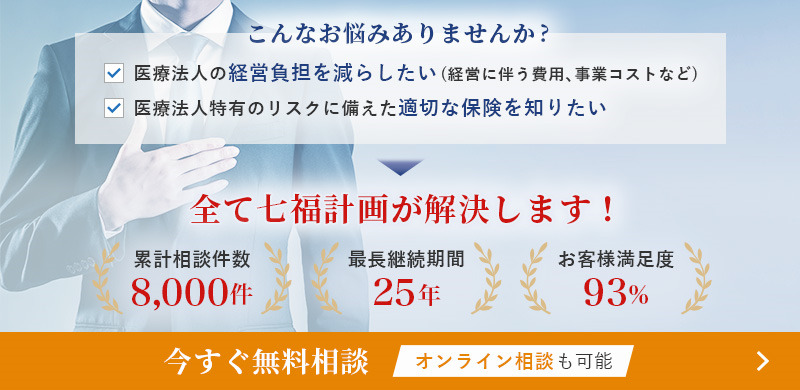
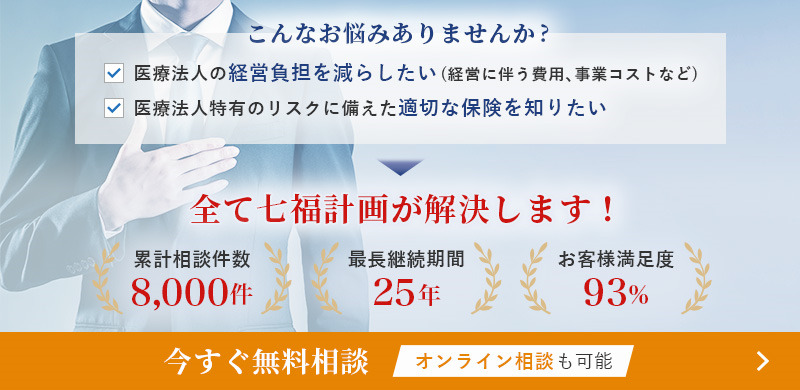
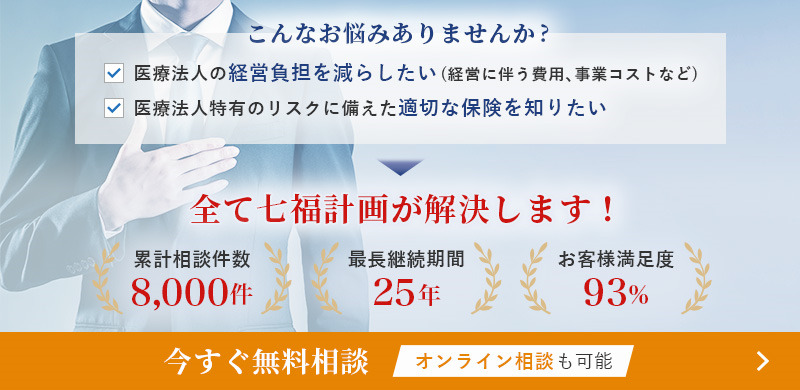
記事まとめ:法人保険についてのご相談は七福計画株式会社へお任せください



今回の記事では、法人保険における経費の基礎知識、経費・損金のルール、法人保険の経費に関するよくある質問などについて解説しました。
2019年に税制が改正されたことにより、経費・損金のルールが変更されました。
企業側は最新情報を踏まえた上で、適切に経費処理を進める必要があります。
社内に専門知識が不足しているという場合、七福計画株式会社にご相談ください。
七福計画株式会社では、法人のリスクやお金に関する相談を受け付けています。
過去20年間で3,000件以上のサポートを提供しており、ノウハウも豊富に所有しています。
法人保険に少しでもお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。










