
福利厚生で法人保険を導入するメリットとデメリットを紹介!
「企業が法人保険を導入する目的とは?」
「法人保険のメリットとデメリットとは?」
と疑問をお持ちの方はいませんか。
生命保険や養老保険、医療保険など、法人保険にはさまざまな種類があります。
法人保険に加入することで福利厚生が充実し、人材の定着率が高まるなどのメリットが多いです。
一方、保険料がかかる、管理が煩雑化するなど、法人保険にはデメリットも存在します。
そこで本記事では、法人保険の種類や会社が従業員にかける生命保険のメリット・デメリット、加入時の注意点などについて解説します。
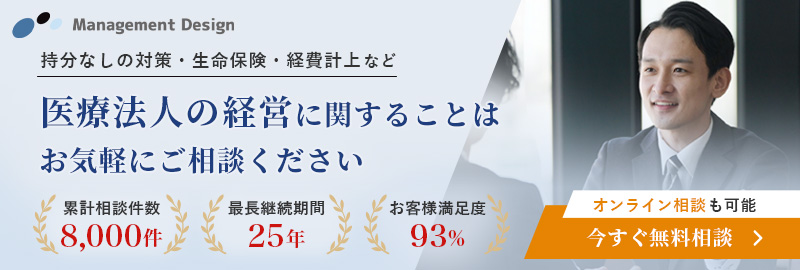
法人保険とは



法人保険とは、法人を契約者とする保険の総称です。
個人を契約者とする保険は「個人保険」と呼ばれています。
法人保険は被保険者に応じて、大きく2種類に分けられます。
- 経営者や役員向けの法人保険(経営者や役員が被保険者)
- 従業員向けの法人保険(従業員が被保険者)
本記事では、後者の「従業員向けの法人保険」について説明していきます。
経営者や役員向けの法人保険については、下記の記事で触れていますので、参考にしてください。
関連記事:法人保険で経営者・役員の退職金を準備する方法を解説
福利厚生で活用できる法人保険の種類
従業員向けの法人保険を導入する目的のひとつに「福利厚生を充実させる」ことが挙げられるでしょう。
以下で、福利厚生で活用できる法人保険の種類を紹介します。
生命保険
生命保険とは、人の生死に備えるための保険です。
従業員が死亡した際に、弔慰金・死亡退職金などとして死亡保険金が遺族等に支払われます。
従業員向けの代表的な生命保険として「総合福祉団体定期保険」が挙げられるでしょう。
法人が契約者となり保険料を支払いますが、従業員は被保険者となり、万が一の際に保険金を受け取ることが可能です。
ちなみに死亡保険金の場合は遺族等、高度障害保険金の場合は従業員本人が受け取ります。
養老保険
養老保険とは、死亡保障と貯蓄の機能を備えた保険です。
万が一亡くなった場合と満期まで生きていた場合のどちらにも備えられます。
満期を退職のタイミングと合わせることで、退職金として活用されることも多いです。
ただし、保障内容が手厚い分、保険料が高額になりやすい点が懸念されます。
医療保険
医療保険とは、従業員の病気やケガに備えるための保険です。
見舞金や賃金補償などに活用されます。
会社員は公的医療保険の健康保険に加入しますが、民間の医療保険があれば福利厚生をさらに充実させることが可能です。
民間の医療保険には、「がん」や「3大疾病」など特定の病気に備えるための保険も存在します。
損害保険
損害保険とは、災害や事故、盗難などのあらゆるリスクに備えるための保険です。
火災に備える「火災保険」や従業員のケガや病気に備える「労災保険」など、損害保険にはさまざまな種類があります。
保険会社によって補償内容や保険料が変わってくるため、比較検討して自社に最適なものを選ぶことが重要です。
会社が従業員にかける法人保険(生命保険)のメリット



それでは、法人保険を導入することでどのようなメリットを得られるのでしょうか?
以下で詳しく確認していきましょう。
優秀な人材を確保できる
法人保険の導入により福利厚生が充実することで、優秀な人材を確保しやすくなります。
近年は求職者のほとんどが福利厚生を細かく確認しており、福利厚生の充実度が応募の決め手となることも少なくありません。
企業が法人保険に加入していれば、手厚い保障を受けられるため、従業員は安心して働くことができます。
さらに、欲しい人材が求めそうな保険に加入すれば、優秀な人材が集まりやすくなるため、企業の採用活動においても大きなアドバンテージとなるでしょう。
人材が定着する
法人保険への加入は採用活動のみならず、人事戦略にとっても大きなアドバンテージとなります。
法人保険によって福利厚生が充実していれば、従業員の満足度が高まり、定着率が高まるためです。
定着率が低いと優秀な人材が流出するだけでなく、企業の評判が下がってしまう可能性があります。
定着率に課題を感じている企業は、法人保険に加入して福利厚生を充実させましょう。
生産性が向上する
法人保険への加入で福利厚生が充実すると、従業員の生産性が向上する可能性があります。
従業員は万が一の時でも保障を受けられるため、十分な休養をとったり、金銭的なサポートを受けたりすることが可能です。
心身の安全は従業員の健康維持にもつながるため、生産性の向上につながります。
また、保障を受けられるという安心感から従業員はモチベーションを維持しやすくなります。
企業への信頼度が高まる
現在は福利厚生が充実しているか、会社が従業員に対してどのようなサポートをするかは、企業の信頼性を左右する重要な要素となっています。
福利厚生が充実している企業であれば、安定した経営基盤があることをアピールできますし、社会的な信頼も得やすいです。
一方、法人保険に加入しておらず福利厚生が不十分だと、「経営基盤が不安定なのでは?」「長期的なキャリアを築きにくいのでは?」と疑問を持たれてしまいます。
そのため、企業の信頼性を高めるためにも法人保険への加入を検討しましょう。
会社が従業員にかける法人保険(生命保険)のデメリット



それでは、会社が従業員にかける法人保険にデメリットはあるのでしょうか?
以下で詳しく確認していきましょう。
保険料がかかる
法人保険に加入する場合、当然ながら保険料について考える必要があります。
どのような法人保険に加入するかによっても費用は変わってきますが、いずれの保険であっても費用負担が大きくなることに変わりはありません。
資金に余裕がない企業にとっては、保険料は痛手となるでしょう。
加えて、近年は少子高齢化が進んでいることもあり、保険料が増加傾向にあります。
保険金の支払い、解約のタイミングによっては、企業の資金繰りに影響する可能性があるため、しっかりと計画を立てることが大切です。
管理が煩雑化する
法人保険に加入すると、管理が煩雑化する点にも注意してください。
例えば、法人保険の加入手続き、申請書類の作成、利用機関とのコミュニケーション、毎月の保険料の支払いなど、さまざまな業務に対応する必要があります。
管理負担を最小限にするために、福利厚生代行サービス企業が提供しているパッケージプランを活用する企業も少なくありません。
福利厚生の内容を最適化できるだけでなく、管理業務を代行してもらえます。
福利厚生で法人保険に導入する際の注意点



以下で、福利厚生目的で法人保険に加入する際の注意点について確認しておきましょう。
目的を明確にする
まず法人保険に加入する目的を明確化しましょう。
法人保険にはさまざまな種類があり、目的によって最適な商品が変わってくるためです。
代表的な加入目的としては、以下が挙げられるでしょう。
- 従業員の死亡や事故、病気などに備える
- 定着率を向上させる
- モチベーションを維持する
- 帰属意識を向上させる
- 優秀な人材を確保する
企業が抱えている課題(人材流出や離職率など)から、目的を明確にすると良いでしょう。
目的が明確になってもどの保険を選べば良いか分からない人は、ぜひ下記より七福計画にお問い合わせください。
福利厚生規定を作成する
福利厚生規定とは、企業が従業員に対して提供している福利厚生の内容等を明記した規定のことです。
企業と従業員間のトラブル防止、経費計上の根拠になるなどの理由で、福利厚生規定が必要とされています。
例えば、退職金の二重払いなどのトラブルを防ぐために、細かく取り決めを定めることが可能です。
福利厚生規程に明記する項目は、以下を参考にしてください。
- 目的
- 施行日
- 対象となる従業員
- 福利厚生の種類
- 保険金額
- 事故発生時の扱い
- 退職時の扱い
- 制度の改廃
最新情報をインプットする
法人保険に加入する前に最新情報をインプットしましょう。
保険や税金に関する法規制が変更されることがあるためです。
これまで法人保険には税負担を軽減する効果がありましたが、2019年に税制が改正されたことにより、保険料を損金に計上できるルールが厳格化されました。
将来的にも、保険料を損金に計上する際のルールが変更になる可能性があります。
しっかりと最新情報には目を向けるようにしましょう。
専門家に相談する
法人保険に関して不明点がある場合は、外部の専門家に相談しましょう。
保険や税金に関する専門知識を備えたプロであれば、自社にとって最適な法人保険を提案してもらえるだけでなく、資金繰りや税金に関してもサポートしてもらえます。
先ほど紹介したように、法規制は将来的にも変化する可能性があります。
最新情報を踏まえた上で適切な対応をするためには、プロの知見が欠かせません。
七福計画株式会社は法人保険をはじめ、資金対策や事業承継、相続など、さまざまなサポートを提供しています。
法人保険でお悩みの方はぜひご相談ください。
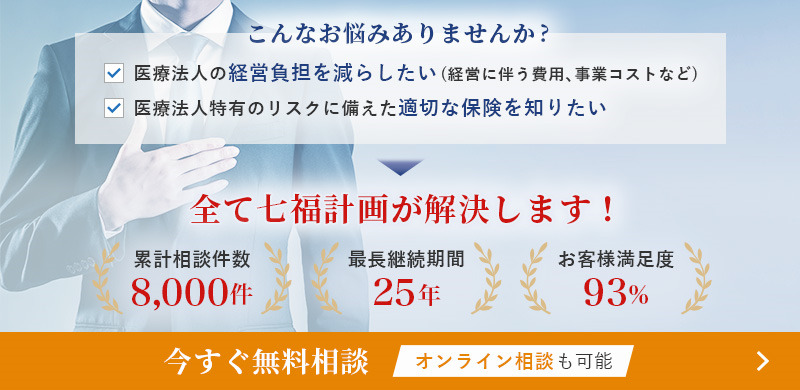
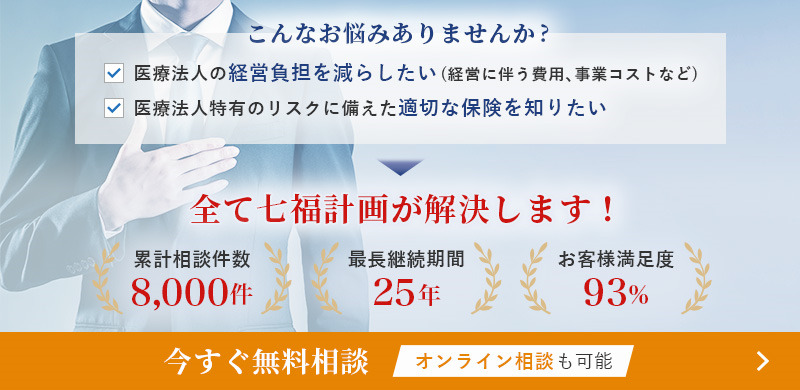
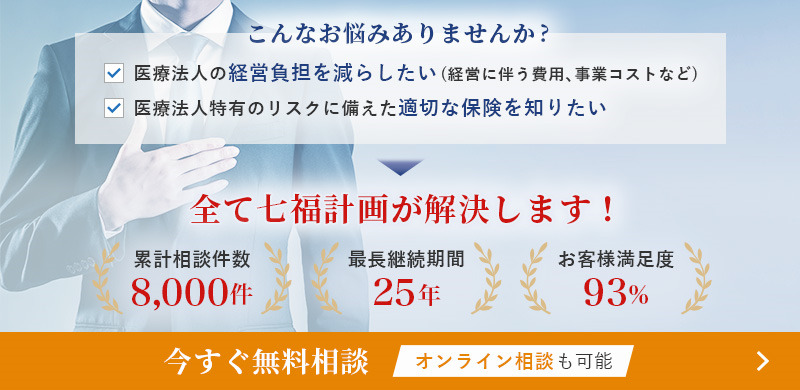
記事まとめ:法人保険についてのご相談は七福計画株式会社へお任せください



今回の記事では、法人保険の種類や会社が従業員にかける法人保険のメリット・デメリット、福利厚生目的で法人保険に加入する際の注意点について解説しました。
法人保険に加入することで、定着率が向上したり、優秀な人材を確保しやすくなったりなど、さまざまなメリットを得られます。
しかし、福利厚生規定の作成や最新情報のインプットなど、法人保険の加入に向けた準備が必要です。
法人保険に関するサポートを提供している七福計画株式会社は、これまでの20年間で3,000件以上ご相談いただいています。
弁護士や税理士のネットワークを活かしながら、法人保険だけでなく、借入金対策、役員退職金準備、事業承継など、リスクやお金に関する課題解決をサポートしています。
法人保険への加入を検討している企業様は、ぜひ一度ご相談ください。










