
法人保険と個人保険の違いとは?メリットやデメリットを詳しく解説
「法人保険と個人保険の違いは?」
「法人保険に加入するメリットはある?」
と疑問をお持ちの方はいませんか。
資金効率は契約形態、給付金の処理方法など、法人保険と個人保険にはさまざまな違いがあります。
今回の記事では、法人保険と個人保険の違いをあらゆる観点から解説します。
法人保険のメリット・デメリット、法人保険と個人保険に関するよくある質問についても説明するので、ぜひ参考にしてください。
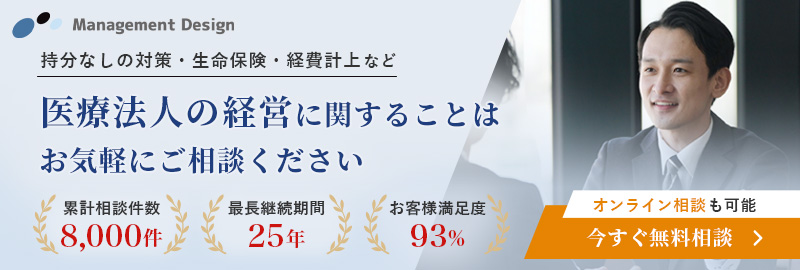
法人保険と個人保険の違いとは



法人保険は法人が契約する保険であるのに対し、個人保険は個人が契約する保険です。
法人保険と個人保険にはさまざまな違いがあります。
以下で、それぞれの違いについて確認していきましょう。
資金効率
個人保険から法人保険に切り替えることで、資金効率がアップする可能性があります。
法人が支払う保険料は、損金算入(経費として計上すること)できるためです。
一方、個人保険の場合は損金の割合は控除の範囲に留まります。
ただし、2019年に税制が改正されたことにより、損金算入のルールが見直されました。
法人保険を税金を抑える目的で利用する企業が増加したためです。
今後も損金算入のルールが厳しくなると言われているため、最新情報を確認するようにしてください。
支払人と受取人
法人保険と個人保険では、保険料の支払人が異なります。
【支払人】
| 法人保険 | 法人が毎月の保険料を支払う |
|---|---|
| 個人保険 | 個人が毎月の保険料を支払う |
受取人に関しては、s個人保険の場合は「個人」が受取人となりますが、法人保険の場合は色々なパターンがあります。
【受取人】
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 |
|---|---|---|
| 法人 | 個人(役員または従業員) | 法人 |
| 法人 | 個人(役員または従業員) | 個人(役員または従業員)または遺族 |
法人保険の種類については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
関連記事:法人保険とは?生命保険と損害保険のそれぞれの種類を紹介
給付金の処理方法
法人保険と個人保険の違いとして、給付金の処理方法が挙げられるでしょう。
一般的に法人保険の方が給付金の受け取りが難しいと言われています。
法人保険の契約者は「法人」であるため、個人が直接給付金を受け取ることはできません。
雑収入として処理した後に、福利厚生の見舞金などとして支給する必要があり、損金処理が複雑です。
手続き
手続き方法も法人保険と個人保険で異なるため、注意しましょう。
基本的に法人保険の方が手続きが煩雑です。
法人が受け取った保険金や給付金は「益金」と見なされるため、課税対象となります。
一方、個人が加入する生命保険の手続きは年々簡素化されており、法人税などの税金を気にする必要がありません。
法人保険の手続きには専門知識が求められるため、外部の専門家を活用する企業も多く見受けられます。
契約形態
法人保険と個人保険の大きな違いの一つが契約形態です。
法人保険では契約者が「法人」であるのに対し、個人保険の契約者は「個人」です。
このため、個人が法人保険に加入することはできません。
また、法人が学資保険などの個人向け保険に加入することもできません。
これにより、契約形態が異なることで、それぞれの保険がカバーする範囲や目的も明確に区別されています。
法人保険のメリット



それでは、個人保険ではなく法人保険に加入するメリットはあるのでしょうか?
法人保険に加入するメリットとデメリットについては、以下の記事でより詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:法人保険に加入するメリットとデメリットを徹底的に解説
万が一の時に備えられる
法人保険に加入するメリットとして、経営者の死亡や病気、ケガ、事故などのあらゆるリスクに備えられる点が挙げられるでしょう。
リスクの内容によっては、事業活動に大きな影響を与えることがあります。
例えば、「経営者が万が一亡くなった際に借入金が残ってしまった」「事故が発生して損害賠償責任が生じた」などの事態に陥った場合、事業を継続することが困難になるでしょう。
しかし、法人保険に加入しておけば、事業を安定化させることができるのです。
事業承継・相続の対策になる
法人保険への加入は、事業承継・相続の対策にもなります。
事業継承をする際は、後継者が贈与税や相続税などの税金を納めなくてはいけません。
中には納税資金を用意できておらず、事業を継続できないといったケースも見られます。
しかし、法人保険に加入しておけば、必要な資金をキャッシュで用意することが可能です。
他にも、納税資金のみならず、遺留分対策金として活用することもできます。
退職金を積み立てられる
法人保険は退職金の資金としても活用できます。
基本的に経営者が受け取れる退職金は、以下の2種類です。
- 死亡退職金:経営者が亡くなった場合に支払われる
- 勇退退職金:経営者が存命中に支払われる
万が一経営者が亡くなった場合、会社が生命保険から受け取った死亡保険金が遺族に支給されます。
経営者が存命の場合、解約返戻金(生命保険の解約時に支払われる資金)が経営者に支給されます。
法人保険の退職金に関しては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:法人保険で経営者・役員の退職金を準備する方法を解説
従業員の福利厚生になる
従業員向けの法人保険に加入する場合、従業員の福利厚生を充実させることが可能です。
従業員が病気になった場合や事故に巻き込まれた場合など、万が一の時にサポートを受けられます。
このように福利厚生が充実していると従業員の満足度が高まり、定着率が向上するだけでなく、採用活動において優秀な人材を確保しやすくなります。
法人保険と福利厚生については、以下の記事で詳細を解説しているのでチェックしてみてください。
関連記事:福利厚生で法人保険を導入するメリットとデメリットを紹介!
法人保険のデメリット



それでは、法人保険に加入するデメリットはあるのでしょうか?
資金繰りが悪化する可能性がある
法人保険に加入すると、当然のことながら費用負担が増大します。
特に手厚い保険に加入した場合、月々の保険料が高くなります。
保険料によりキャッシュが減少するため、資金繰りが悪化する恐れがあるのです。
事業資金に余裕がなくなる、業績悪化時の負担感が大きくなるなどの事態に陥ってしまうと、事業運営に影響が及びます。
そういった事態を防ぐためにも、保険料と補償内容のバランスを見て最適な法人保険を見極めましょう。
払込保険料が高い
解約時期によっては、解約返戻金(解約時に受け取れる資金)よりも払込保険料(法人が月々支払う保険料)の方が高くなる可能性があります。
つまり、支払った分が返ってこない可能性があるということです。
解約返戻率がピークを迎えるタイミングは保険の種類によって異なります。
一般的には、法人保険に加入してから数年〜数十年後に解約返戻率が高くなりやすいです。
解約返戻金を退職金や事業資金に充てようと考えている法人は、解約の時期を踏まえた上で加入することをおすすめします。
法人保険と個人保険に関するよくある質問



ここでは、法人保険・個人保険に関するよくある質問に回答します。
法人保険は税金対策にならない?
以前までは、税金対策を目的として法人保険に加入する企業が見受けられました。
しかし、2019年に税制が改正されたことにより、損金算入のルールが厳格化されました。
その結果、法人保険における税金対策の効果が薄れてしまったのです。
そのため、税金対策目的で法人保険に加入することはおすすめできません。
法人保険には税金対策以外にもさまざまなメリットがあるため、目的を見直しましょう。
個人事業主は法人保険と個人保険のどちらを検討すべき?
基本的には法人保険の契約者は「法人」で、個人保険の契約者は「個人」です。
ただし、個人事業主でも法人契約できる商品はあります。
個人事業主で損金計上するためには、家族以外の第三者を被保険者とする必要があるなど、さまざまな注意点があるため、専門家に相談すると良いでしょう。
生命保険を法人契約した場合、受取人は個人?
生命保険を法人契約した場合、受取人は「①法人」もしくは「②個人」となります。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 |
|---|---|---|
| 法人 | 個人(役員または従業員) | 法人 |
| 法人 | 個人(役員または従業員) | 個人(役員または従業員)または遺族 |
基本的に受取人を法人、個人にするかは契約時に決めます。
受取人によって経理処理の方法が異なるため注意してください。
掛け捨て型の法人保険はどのように活用できる?
掛け捨て型の法人保険とは、保険金が支給される事象が発生しなかった場合、支払った保険料が掛け捨てになるタイプの保険です。
つまり、解約返戻金が返ってきません。
ただ、貯蓄型の保険と比較すると、掛け捨て生命保険の方が保険料が少ないです。
保険料の支払いにより資金繰りが悪化する恐れがある場合などに活用できるでしょう。
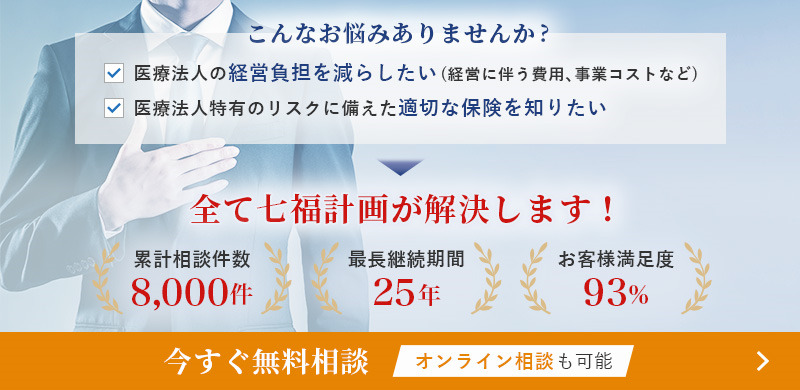
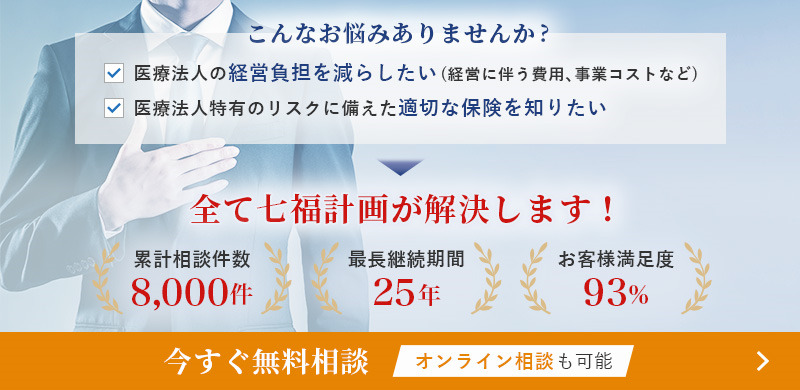
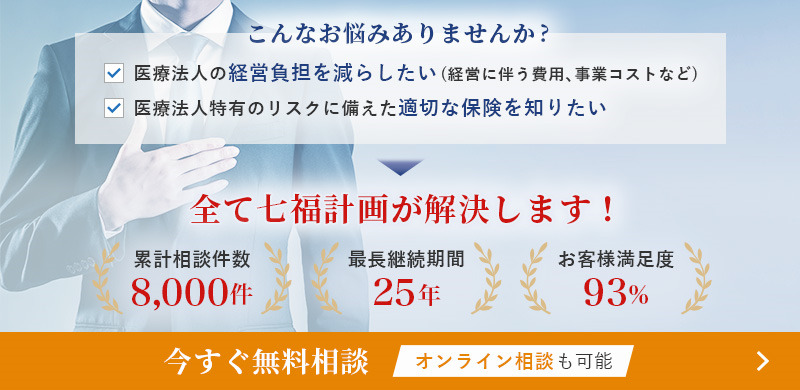
記事まとめ:法人保険についてのご相談は七福計画株式会社へお任せください



今回の記事では、法人保険と個人保険の違い、法人保険のメリット・デメリット、法人保険と個人保険に関するよくある質問について解説しました。
法人保険と個人保険では、契約形態や手続き、給付金の処理方法などが異なります。
法人保険の方が手続きなどが煩雑な傾向にあるため、しっかりとリサーチする必要があります。
法人保険の手続きで不安を感じている企業は、専門家を活用しましょう。
七福計画株式会社は、リスクやお金などさまざまな課題解決を支援しています。
これまで20年間で3,000件以上のサポートを手がけており、専門的な知見や豊富なノウハウを持っています。
法人保険でお困りの方は、ぜひご相談ください。










